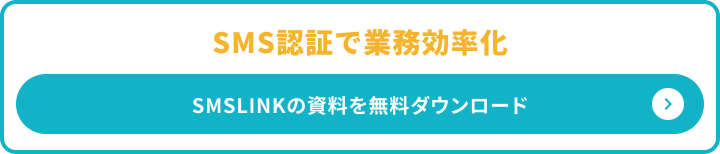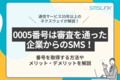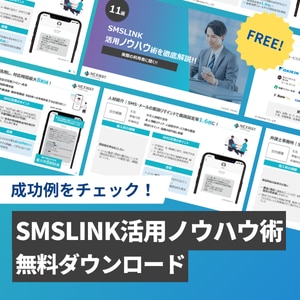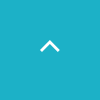継続的顧客管理(CDD)とは?必要な理由や、通知の課題を解決する方法を解説
継続的顧客管理(CDD)の質問票送付には高到達率のSMSが最適!
>【法人向け】1通6円~SMSを送れるSMSLINKの資料を無料でダウンロードする
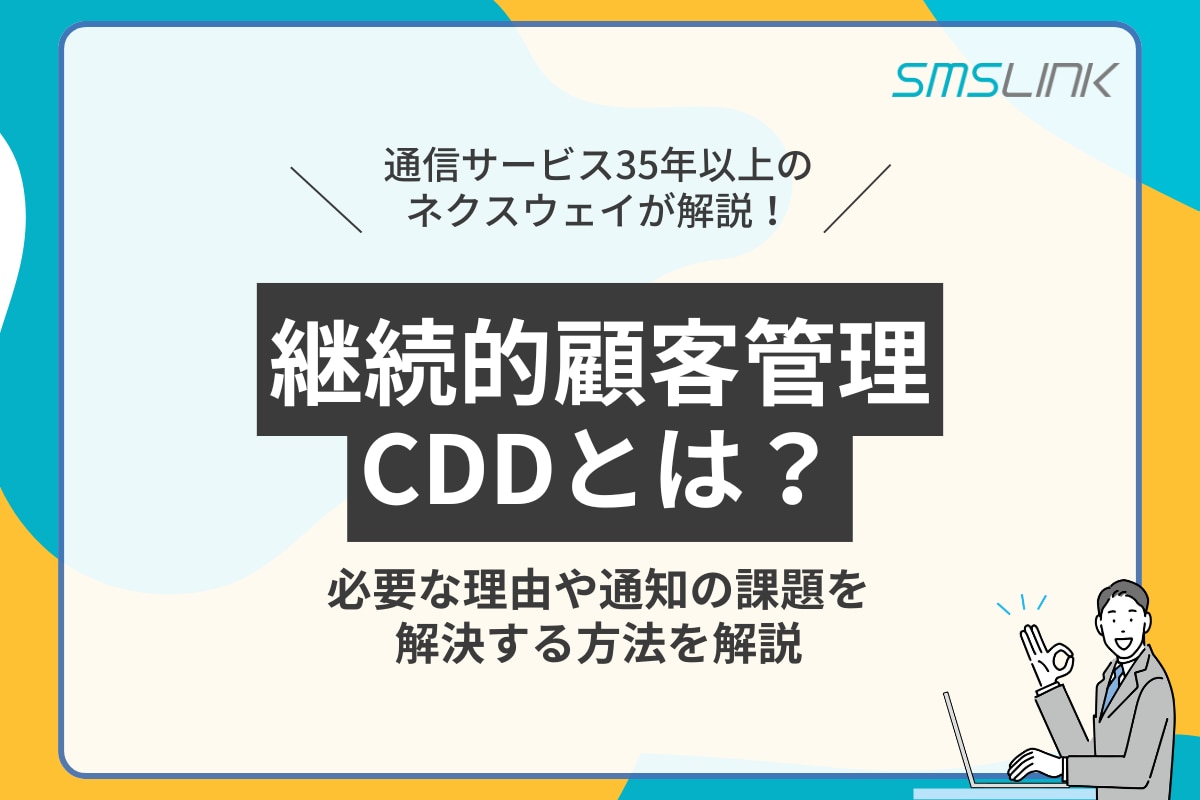
こんにちは。「SMSLINK」ライターチームです。
継続的顧客管理(CDD)は、企業や金融機関が顧客の取引リスクを評価し、不正防止やコンプライアンス強化を目的として実施するプロセスです。CDDを適切に行うことで、金融犯罪の防止や規制順守が可能になります。しかし、顧客への通知やデータ管理には課題も多く、効率的な運用が求められます。
本記事では、CDDの概要やプロセス、課題の解決策としてのSMS活用について詳しく解説します。
継続的顧客管理(CDD)の質問票送付には高到達率のSMSが最適!
>【法人向け】1通6円~SMSを送れるSMSLINKの資料を無料でダウンロードする
目次[非表示]
- 1.継続的顧客管理(CDD)の概要
- 1.1.基本的な定義
- 1.2.CDDを導入する目的
- 1.3.適用範囲
- 2.継続的顧客管理(CDD)のプロセス
- 3.CDDにおける顧客のリスク評価の種類
- 3.1.顧客への質問票の通知
- 3.2.顧客からの回答回収
- 3.3.回答のデータ化・審査
- 3.4.CDDの報告義務
- 4.継続的顧客管理(CDD)の法律と規制
- 4.1.国際的な法律
- 4.2.日本におけるCDDの法的枠組み
- 5.継続的顧客管理(CDD)のメリット
- 5.1.不正取引の防止につながる
- 5.2.法律・規制の順守
- 6.継続的顧客管理(CDD)の課題
- 6.1.顧客の負担増
- 6.2.データ管理が煩雑になる
- 6.3.従業員への教育
- 6.4.顧客への連絡手段
- 7.継続的顧客管理(CDD)の質問票通知にはSMSが最適
- 7.1.SMSが最適な理由
- 7.2.CDDにおけるSMS活用の具体例
- 8. CDDの質問票送付ならSMSLINKがおすすめ
- 9.まとめ
継続的顧客管理(CDD)の概要

継続的顧客管理(CDD)は、企業や金融機関が顧客の取引リスクを評価し、継続的に監視するプロセスです。CDDを導入することで、マネーロンダリングや不正取引を未然に防ぐとともに、各国の法律や規制を順守できます。
ここでは、CDDの基本的な定義、導入目的、適用範囲について解説します。
基本的な定義
CDD(Customer Due Diligence)とは、顧客の身元や取引の実態を把握し、リスク評価を行う継続的な管理プロセスのことです。主に金融機関や法人が、不正行為や違法取引を防ぐために実施します。CDDは初回取引時だけでなく、取引が続く限り定期的に見直しを行う点が特徴です。
CDDを導入する目的
CDDを導入する主な目的は、以下の通りです。CDDを適切に実施することで、金融犯罪のリスクを減らし、法的なコンプライアンスも強化できます。
- 不正取引の防止 マネーロンダリングやテロ資金供与を未然に防ぐ
- 法律・規制の順守 金融機関や企業が法的義務を果たすため
- 信用リスクの管理 企業が顧客との取引の安全性を確保する
- レピュテーションリスクの低減 企業の信頼性を維持し、社会的責任を果たす
適用範囲
CDDは、以下のような企業や取引内容に適用されます。
対象となる企業
金融機関
銀行、信用金庫、証券会社、保険会社など、金融サービスを提供するすべての機関が含まれます。
特定事業者
商品先物取引業者や暗号資産交換業者など、特定の業種に属する事業者も対象です。これらの事業者は、法律に基づき、顧客の取引時確認や疑わしい取引の届出を行う義務があります。法人
法人顧客に対しても、実質的支配者(大口株主など)の確認が求められます。特に、外国の重要な公的地位にある方(PEPs)との取引に際しては、追加の確認が必要です。
対象となる取引内容
- 高額取引
多額の現金や小切手を用いた取引、収入や資産に比して高額と思われる取引が特に注視されます。 - 頻繁な取引
短期間に頻繁に行われる取引や、取引の目的が不明瞭な場合も、詳細な確認が求められます。 - 疑わしい取引
取引の内容や状況に疑念が生じた場合、金融機関は顧客に対して追加の情報提供を求めたり、取引を制限したりすることがあります。
継続的顧客管理(CDD)の質問票送付には高到達率のSMSが最適!
>【法人向け】1通6円~SMSを送れるSMSLINKの資料を無料でダウンロードする
継続的顧客管理(CDD)のプロセス
継続的顧客管理(CDD)は、顧客のリスクを適切に管理するために、いくつかのステップを経て実施されます。主なプロセスとして、顧客の身元確認、リスク評価、質問票の通知と回答回収、データの審査、報告義務が含まれます。
これらの手順を適切に実施することで、企業や金融機関は法令順守を確保し、不正リスクを低減できます。
顧客の身元確認
まずは、顧客の身元を確認する必要があります。本人確認の方法は、取引のリスクレベルに応じて異なります。この段階で不審な点があれば、追加調査を行う必要があります。
- 個人顧客の場合
本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)の提出 - 法人顧客の場合
登記簿謄本、代表者の身元確認書類の提出 - 高リスク顧客の場合
追加の情報(収入証明、取引履歴など)の提出
顧客のリスク評価
顧客の身元確認が完了したら、リスク評価を行います。リスク評価では、以下のような要素を考慮し、低・中・高のリスクカテゴリに分類したうえで、適切な監視レベルを設定します。
- 顧客の居住国・取引国|マネーロンダリングリスクの高い国との関係
- 取引の種類・金額|高額取引や頻繁な送金の有無
- 業種・職業|ハイリスク業種(カジノ、貴金属取引など)との関係
- 過去の取引履歴|不審な取引の有無
継続的顧客管理(CDD)の質問票送付には高到達率のSMSが最適!
>【法人向け】1通6円~SMSを送れるSMSLINKの資料を無料でダウンロードする
CDDにおける顧客のリスク評価の種類

顧客デュー・ディリジェンス(CDD)におけるリスク評価は、顧客が金融機関に与えるリスクを特定し、管理するための重要なプロセスです。リスク評価は、顧客の特性や取引内容に基づいて行われ、以下のような種類に分類されます。
1. リスクレベルの分類
リスクレベル | 説明 | 適用される管理手法 |
|---|---|---|
低リスク顧客 | 安定した収入源を持ち、 過去に問題行動がない顧客。 | 簡素な管理 SDD: Simplified Due Diligence |
中リスク顧客 | 特定の条件(例: 外国の高リスク地域からの資金移動など)に該当する顧客。 | 標準的な管理 SDD: Standard Due Diligence |
高リスク顧客 | 政治的に重要な人物(PEP)や、 マネー・ローンダリングやテロ資金供与に 関与した疑いのある顧客。 | 厳格な管理 EDD: Enhanced Due Diligence |
2. リスク評価の要素
- 顧客の身元確認
顧客の身分証明書や住所証明書を確認し、本人確認を行います。 - 取引の目的と性質
顧客が口座を開設する目的や、取引の性質を理解することが重要です。例えば、ビジネスの種類や取引の頻度などが考慮されます。 - 資金の出所
顧客の資金源が合法であるかどうかを確認します。資金の出所が不明瞭な場合、リスクが高まります。 - 顧客の行動パターン
顧客の取引履歴や行動に異常がないかを監視します。例えば、頻繁な住所変更や不自然な取引パターンは、リスクの兆候と見なされます。
顧客への質問票の通知
CDDの一環として、企業や金融機関は顧客に定期的に質問票を送付し、現在登録されている情報から変更がないかの確認をする必要があります。
質問票の通知頻度は前述のリスク評価によって異なり、高リスク顧客に対しては年に1回、中リスク顧客は2年に1回、低リスク顧客は3年に1回という頻度で送付を行います。また送付方法には、郵送、Eメール、SMSなどがあり、迅速かつ確実に届く手段を選ぶことが重要です。
質問票の内容例
- 取引目的の確認
- 事業内容や収益の出所
- 職業・勤務先情報
- 取引の目的
- 実質的支配者(UBO)の特定 など
顧客からの回答回収
質問票を送付した後は、顧客からの回答を回収します。回答の回収が滞ると、CDDの適用が遅れ、リスク評価に影響を与えるため、迅速な回収が求められます。
回収方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
オンライン(eKYC含む) |
|
|
郵送返信 |
|
|
回答のデータ化・審査
回収した回答は、データ化した上で審査を行います。審査のポイントは以下の通りです。不審な点があれば、追加情報の提出を求めたり、関係当局に報告したりすることもあります。
- 記入漏れや不備の有無
- 提出された情報と顧客の取引内容の整合性
- 過去のCDD情報との比較
CDDの報告義務
CDDの最終ステップとして、特定の取引や顧客がリスク基準を超えた場合、企業や金融機関は当局に報告する義務があります。報告を怠ると、企業が法的責任を問われる可能性があるため、適切な管理体制を整えることが重要です。
報告が必要なケースの例
- 疑わしい取引の発見 マネーロンダリングの疑いがある取引
- 高額送金の検出 一定額以上の送金が頻繁に行われる場合
- 規制対象国との取引 制裁リストに含まれる国や個人との取引
継続的顧客管理(CDD)の質問票送付には高到達率のSMSが最適!
>【法人向け】1通6円~SMSを送れるSMSLINKの資料を無料でダウンロードする
継続的顧客管理(CDD)の法律と規制

CDD(継続的顧客管理)は、各国の法律や国際規制に基づいて実施される必要があります。特に金融機関や特定事業者に対して、マネーロンダリング対策(AML)やテロ資金供与対策(CFT)としての義務が課されています。
ここでは、国際的な法律や日本におけるCDDの法的枠組みについて解説します。
国際的な法律
CDDに関連する国際的な法律や規制の枠組みとして、以下のようなものがあります。これらの国際規制により、各国の金融機関や企業はCDDを強化し、不正取引の防止に努める必要があります。
FATF(金融活動作業部会)勧告
国際的なマネーロンダリング対策とテロ資金供与対策を推進する機関で、マネー・ローンダリングやテロ資金供与に対抗するための国際的な基準を策定しています。
- 各国にCDDの実施と疑わしい取引の報告を求める
- リスクベースアプローチ(RBA)を推奨
バーゼル銀行監督委員会(BCBS)の指針
国際的な銀行監督の基準を策定し、金融機関の健全性を確保するための指針を提供しています。
- CDDのプロセスとして、顧客識別、リスク評価、継続的監視の強化を推奨
- マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に対するリスク管理のガイドラインを提供
米国の銀行秘密法(BSA)
1970年に制定された米国の法律で、金融機関に対してマネーロンダリングやテロ資金供与を防止するための報告義務を課しています。
- 不審な活動報告(SAR) 金融機関は、疑わしい取引に気付いた場合の報告義務
- 外国銀行口座レポート(FBAR) 米国市民が国外に銀行口座を持つ場合、その口座の情報の報告を義務化
- 通貨取引報告(CTR) 特定の高額取引や疑わしい取引の報告を義務化
EUマネーロンダリング指令(AMLD)
EU加盟国におけるマネーロンダリング防止のための法的枠組みを提供する一連の指令です。
- 欧州連合(EU)内の金融機関に対し、CDDの導入を義務付け
- 顧客のリスクレベルに応じた監視を推奨
日本におけるCDDの法的枠組み
日本でも、CDDに関する規制が複数の法律によって義務付けられています。特に、金融機関や特定事業者は厳格な顧客管理を求められます。
犯罪収益移転防止法(犯収法)
マネーロンダリングを防ぐため、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するために制定された法律で、金融機関や特定事業者に対して顧客の本人確認や疑わしい取引の報告を義務付けています。
- 顧客の本人確認(KYC)
- 顧客のリスクを評価し、リスクに応じた管理措置の実施
- 疑わしい取引の届出(STR)
- 取引記録の保存
金融商品取引法
金融商品取引の公正を確保し、投資家を保護するための法律です。
- 証券会社や投資信託会社に対し、CDDの実施を求める
- 高リスク取引の監視と顧客情報の定期更新を義務付け
預金取扱金融機関向けのガイドライン(金融庁)
預金取扱金融機関に対して、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインを提供しています。
- 銀行や信用金庫などに対し、CDDを含むAML/CFT対策を強化
- 取引のモニタリングや疑わしい取引の報告を求める
特定商取引法
特定商取引法は、消費者と事業者間の取引における不正行為を防止するための法律です。この法律においても、事業者は顧客の身元確認を行うことが求められ、特に訪問販売や通信販売においては、顧客の情報を適切に管理する必要があります。
資金決済法
資金決済法は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保するための法律で、特に電子マネーやプリペイドカードの発行に関連しています。この法律も、顧客の身元確認や取引の透明性を確保するための措置を求めています
CDDの法律や規制は、国際的にも日本国内でも厳格化が進んでいます。特に金融機関や高リスク業種の事業者は、適切な顧客管理を行い、法令順守を徹底する必要があります。次に、CDDを導入することによるメリットについて詳しく解説します。
継続的顧客管理(CDD)の質問票送付には高到達率のSMSが最適!
>【法人向け】1通6円~SMSを送れるSMSLINKの資料を無料でダウンロードする
継続的顧客管理(CDD)のメリット
CDD(継続的顧客管理)を適切に実施することで、企業や金融機関はさまざまなメリットを得られます。主に、不正取引の防止や法令順守の強化などが挙げられます。ここでは、CDDを導入することで得られる具体的な利点について解説します。
不正取引の防止につながる
CDDを実施することで、不正取引やマネーロンダリングの防止につながります。顧客のリスクを定期的に評価し、疑わしい取引を早期に発見できるためです。
身元確認の強化
- 顧客の本人確認を徹底することで、架空口座やなりすまし取引を防止
- 企業の信頼性向上につながる
リスク評価の精度向上
- 高リスク顧客を特定し、適切な対策を講じることが可能
- 取引パターンの分析により、通常とは異なる動きを検知
疑わしい取引の早期発見
- 継続的な監視により、不審な資金移動を特定
- フィルタリングシステムやAIを活用し、リスクの高い取引をリアルタイムで検知
このように、CDDを実施することで、企業や金融機関はリスク管理を強化し、不正行為を未然に防ぐことができます。
法律・規制の順守
CDDを適切に行うことで、企業は各国の法律や規制を順守し、コンプライアンス違反のリスクを軽減できます。
法的義務の履行
- 犯罪収益移転防止法(犯収法)やAML(マネーロンダリング防止)規制に対応
- 法律に基づいた顧客情報の管理・更新を実施
行政処分のリスク回避
- 規制当局の監査において、適切なCDDを実施していることを証明できる
- 適切なリスク管理を行うことで、罰則や制裁措置を回避
企業の信頼性向上
- 法令順守を徹底することで、投資家や取引先からの信頼を獲得
- CDDの適正な実施は、企業価値の向上にも寄与
コンプライアンス違反は、企業にとって大きなリスクとなります。そのため、CDDを適切に運用することで、法的リスクを最小限に抑えることが重要です。
CDDを導入することで、不正取引の防止や法律・規制の順守が可能になります。特に金融機関や高リスク業種の企業にとっては、リスク管理の強化が必須となるため、適切なCDDの実施が求められます。次に、CDDの課題について詳しく解説します。
継続的顧客管理(CDD)の質問票送付には高到達率のSMSが最適!
>【法人向け】1通6円~SMSを送れるSMSLINKの資料を無料でダウンロードする
継続的顧客管理(CDD)の課題

CDD(継続的顧客管理)は、企業や金融機関にとって重要なプロセスですが、実施にはいくつかの課題が伴います。特に、顧客対応やデータ管理、従業員教育、顧客への連絡手段の選択などが問題となることが多いです。ここでは、代表的な課題について解説します。
顧客の負担増
CDDを実施する際、顧客に対して追加情報の提出や身元確認を求めることがあります。しかし、これを負担と感じる顧客が多く、対応を拒否されたり、手続きを放置されたりするケースが発生します。
顧客からの拒絶を防ぐには、簡単でスムーズな手続きを提供し、CDDの重要性を伝えることが不可欠です。
主な理由
- 手続きが煩雑で面倒に感じる
- 個人情報を提供することへの抵抗感
- CDDの必要性を十分に理解していない
対策
- 手続きの簡略化(オンラインフォームやSMSでの通知など)
- CDDの必要性を明確に説明し、顧客の理解を促す
- 顧客の負担を軽減するため、複数の提出方法を用意
データ管理が煩雑になる
CDDの実施に伴い、顧客情報の管理が煩雑になりやすいです。特に、多くの顧客を抱える企業では、大量のデータを正確に処理・管理する必要があります。適切なデータ管理体制を整えることで、CDDの運用効率を向上させることが可能です。
データ管理の課題
- 顧客情報の更新が追いつかない
- 収集したデータの整理・分析に時間がかかる
- セキュリティ対策が不十分だと、情報漏洩のリスクが高まる
対策
- データ管理システムの導入(CRMやデータベースの活用)
- 定期的なデータ更新ルールの設定
- 高度なセキュリティ対策(暗号化やアクセス制限の強化)
従業員への教育
CDDを適切に実施するためには、従業員の理解と協力が欠かせません。しかし、CDDの重要性や手続きが十分に浸透していないと、対応にばらつきが生じることがあります。従業員への継続的な教育を行うことで、CDDの精度向上と業務の効率化を図ることができます。
教育不足による問題点
- 誤った手続きが行われるリスク
- 顧客対応に時間がかかり、業務負担が増加
- コンプライアンス違反の可能性
対策
- 定期的な研修の実施(CDDの目的・手順・法規制の説明)
- チェックリストやマニュアルの整備
- ITツールの活用による業務の標準化
顧客への連絡手段
CDDを実施する際、顧客に対して必要な手続きを通知することが求められます。しかし、連絡手段を誤ると、通知が届かない、見逃される、対応が遅れるといった問題が発生します。
適切な連絡手段を選択することで、顧客の対応率を高め、CDDの実施を円滑に進めることができます。
連絡手段 | 課題 |
|---|---|
電話 | 忙しい顧客が出られない、架電コストが高い |
メール | 迷惑メール扱いされる、開封率が低い |
郵送 | 到着までに時間がかかる、コストがかかる |
SMS | 視認性が高いが、長文の案内には不向き |
対策
- SMSを活用し、重要な通知を確実に届ける
- 複数の連絡手段を組み合わせ、見逃しを防ぐ
- 期限を設定し、リマインダーを送る
CDDを実施する際には、顧客の負担を減らしながら、データ管理や従業員教育、適切な連絡手段の選定を行うことが重要です。次に、CDDにおいてSMSが有効な理由について解説します。
継続的顧客管理(CDD)の質問票送付には高到達率のSMSが最適!
>【法人向け】1通6円~SMSを送れるSMSLINKの資料を無料でダウンロードする
継続的顧客管理(CDD)の質問票通知にはSMSが最適

CDDを実施する上で、顧客への質問票通知は不可欠です。しかし、通知手段を誤ると、顧客が見落としたり、対応を後回しにしたりするリスクが生じます。そのため、迅速かつ確実に通知を届ける手段としてSMSが最適です。ここでは、SMSが適している理由と具体的な活用例について解説します。
SMSが最適な理由
SMSは、他の通知手段と比較して高い視認性と即時性を持つため、CDDの質問票通知に適しています。
SMSのメリット
- 視認性が高い
メールよりも届く件数が少ないため、目に止まりやすく、確実に読まれやすい。 - 即時性がある
送信後、ほぼリアルタイムで受信者に届くため、迅速な対応を促せる。 - 迷惑メールフィルターの影響を受けにくい
メールはスパム扱いされる可能性があるが、SMSは受信トレイに直接届く。 - 顧客の手元に直接届く
スマートフォンで受け取れるため、見逃しにくい。
CDDにおけるSMS活用の具体例
SMSは、単なる通知手段としてだけでなく、CDDの各プロセスで活用できます。ここでは、具体的な活用例を紹介します。
1.質問票の送付
CDDでは、顧客のリスク評価のために質問票を送付し、回答を求める必要があります。SMSを活用することで、迅速かつ確実に顧客へ通知できます。
活用例
- SMSで質問票のURLを送信
- 顧客がスマホやPCでフォームにアクセス
- 回答を入力し、オンラインで送信
2.郵送物の不着時の連絡
CDDの通知を郵送で行う場合、住所変更や不在などの理由で届かないケースがあります。その際、SMSを活用して再送依頼や対応を促すことができます。
活用例
- 郵送物が不着だった場合、SMSで「〇〇の手続きが必要です」と通知
- 受信者がSMS内のURLから問い合わせフォームへアクセス
- 正しい住所を入力し、再送依頼を送信
SMSは、閲覧率・即時性・確実性の面でCDDの質問票通知に最適な手段です。質問票の送付だけでなく、郵送不着時のフォローにも活用できるため、企業の業務効率化に貢献します。次に、SMSと郵送をワンストップで対応できるネクスウェイのサービスについて解説します。
継続的顧客管理(CDD)の質問票送付には高到達率のSMSが最適!
>【法人向け】1通6円~SMSを送れるSMSLINKの資料を無料でダウンロードする
CDDの質問票送付ならSMSLINKがおすすめ
SMSでのCDDの質問票送付をご検討なら、ぜひネクスウェイの「SMSLINK」をご利用ください。
初期費用や月額固定料金は0円で、送ったSMSの数によって利用料が確定するため、コストを抑えながらSMS配信を始めたいという方におすすめです。
一斉送信はもちろん、短縮URLの自動生成などの便利な機能が充実しており、送信元番号の変更にも対応しています。SMSの配信によってユーザーへの連絡の到達率を上げたいとお考えの方は、ぜひ「SMSLINK」の導入をご検討ください。
【SMSLINKの特徴】
- 7年で3,500社超の導入実績(※2025年9月時点)
- 国内携帯キャリアと直接接続による安定した通信網を利用
- 初期費用、月額固定費0円、1通あたり6円~(※月間の送信通数によって異なります)
- 直感的に利用できるわかりやすい管理画面
- API連携 / 最短3日で開発できる簡易API
ネクスウェイならSMS・郵送をワンストップでおまかせ
企業によってはSMSと郵送の両方を使い分ける必要があり、それぞれの管理や運用が煩雑になることがあります。ネクスウェイなら、SMSと郵送をワンストップで提供できるため、企業の負担を軽減しながらCDD業務を効率化できます。
SMSと郵送を組み合わせた最適な通知手段を提供
- SMSでの通知が可能な顧客には、URL付きのメッセージを送信
- SMSを受信できない顧客には、郵送で質問票を送付
- どちらの方法でも回答が得られない場合、別の手段でフォローアップ
ネクスウェイを活用すれば、SMSと郵送の組み合わせによる効果的な通知が可能になります。企業の負担を減らしながら、CDDの業務を円滑に進められるため、効率化と確実性を両立できます。CDDの質問票通知でお悩みの方は、ネクスウェイのサービスをぜひご活用ください。
継続的顧客管理(CDD)の質問票送付には高到達率のSMSが最適!
>【法人向け】1通6円~SMSを送れるSMSLINKの資料を無料でダウンロードする
まとめ
継続的顧客管理(CDD)は、金融機関や企業が顧客リスクを適切に評価し、不正取引を防ぐために必要なプロセスです。CDDでは、顧客の身元確認やリスク評価、質問票の通知・回収、データの審査・報告などの手順を踏むことで、コンプライアンスを順守しながら適切な取引を維持できます。
CDDの質問票通知にはSMSの活用が有効です。SMSは高い開封率を誇り、リアルタイムで顧客に通知できるため、質問票の送付やリマインド通知に適しています。また、ネクスウェイのサービスを活用すれば、SMSと郵送の両方を一元管理し、効率的な通知が可能になります。
***
ネクスウェイが提供するSMS配信サービス「SMSLINK」は、マニュアルレスで簡単に操作できる、高性能なSMS送信サービスです。わかりやすいAPIリファレンスも特徴で、最短3日でAPI連携した実績もあります。また業界最安値水準(6円/通~)での利用が可能です。
FAX、郵送、メールなどの通信インフラを35年間に渡って提供してきた実績があり、保守・運用・サポートまでお任せできます。SMSの活用についてぜひご相談ください。